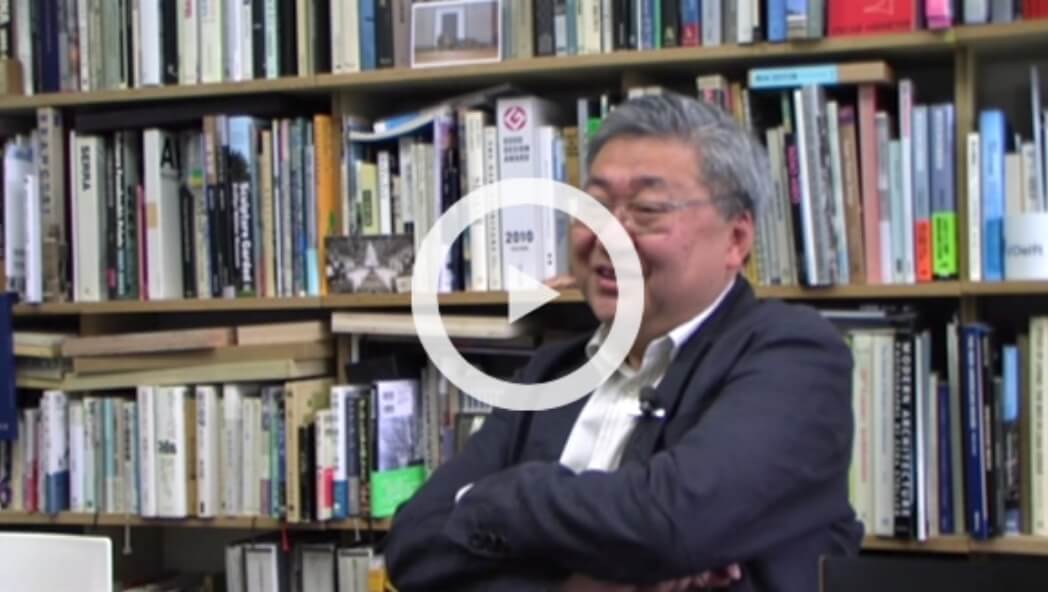メディア
From 1994 to 2023

すべての関係者の皆さまに感謝を込めて。
記念対談

「空間デザイン・コンペティション」開催30回を記念し、第23回からコーディネーターを務める建築批評家・五十嵐太郎氏と、かつての本コンペ受賞者で第30回審査委員長、いまや世界的に活躍する建築家・藤本壮介氏との対談が実現。当時の受賞作品や思考していたこと、建築コンペ全般にまつわる話から生成AIの可能性に至るまで、興味深いお話を和やかに語っていただきました。
21世紀の新しい建築を打ち立てる
そんな気概があった(藤本)
五十嵐:藤本さんは学生の頃から、いろいろコンペに参加されていたと思うのですが、実際のところはいかがでしたか。
藤 本:むしろ独立してからの方が多いですね。学生の頃はなかなかそっちの世界に踏み出せなくて。でも卒業後は時間がたくさんできたので、当時行われていたアイデアコンペにはよく応募していました。
五十嵐:雑誌に結構コンペの情報が載っていましたからね。
藤 本:そうですよね。日本電気硝子さんもそうですけど、有名なものはチェックしていました。
五十嵐:コンペキラーだったとか?
藤 本:いえ、雑誌でいつも入選している人の名前を見ては「すごいなぁ」と思っていました(笑)。一等になったのは一回、佳作が数回くらいです。別のコンペですが佳作入選の知らせを受けて、「やった!」と喜んでいたのも束の間、あとで大学の同期が同じコンペで二等を受賞していたことを知って。さらに一等の人はもう一点作品を提出していて、一等と佳作のダブル受賞。打ちのめされた感が半端なかったというのが僕の最初のアイデアコンペの記憶です(笑)。
五十嵐:時期的にはいつ頃が多かったですか。
藤 本:94年の春に大学を卒業したので、90年代後半ですね。
五十嵐:具体的にどこの実施コンペに参加されましたか。
藤 本:国立国会図書館の関西館です。全然ダメでしたけど。
五十嵐:そんな大きい建築にも応募できたんですね。
藤 本:そうなんです。何も実績のない若者が出せたという。2000年の青森県立美術館 ※1 も実績要件もなく出せました。
五十嵐:今回、97年に空間デザインコンペで受賞された作品 ※2 を拝見しましたが、やっぱり藤本さんらしいなと。これがHouse N ※3 にも繋がっているんだろうなと改めて感じました。
藤 本:街の中に背の高いガラスのベンチみたいなものが立っているという案でした。当時、住んでいた西新宿5丁目辺りのくねくねした路地を毎日散歩していたのですが、その風景がこれまで考えていた都市よりも身体に近いように思えて、外出しているのに半分家の中に居るような感覚に包まれたんです。家具のスケール感と建築や都市のスケール感が近づいてきて、町や都市全体が家になる。その一方で、自分の体が都市に開かれて都市の一部に重なっていく。そんな街のスケール感を面白いと思っていました。コンペのテーマは「都市の中のガラスブロック」というものでしたが、居場所のようなものが先にアイデアとして浮かび、そこから小さなガラスブロックが都市にあることと、小さな人間が都市にいることが重なって、アイデアをガラスブロックに落とし込んでいきました。その時の自分の状況も表現していたのかもしれませんね。
五十嵐:最初の頃は実作がないから、コンペは励みにも自己研鑽を積む場にもなりますよね。
藤 本:コンペのテーマを自分が考えていることに引き寄せつつ、自分の思考を具現化していく作業を懸命にやっていたという面がありました。「21世紀の新しい建築をここから打ち立ててやる!」みたいな気持ちもあって、たとえば「ガラス」という素材をまったく新しく解釈することで、まったく新しい建築が作れるんじゃないか? というワクワク感もあったりして。
五十嵐:アイデアコンペは良くも悪くも作る義務がない分、自由に発想できますからね。
藤 本:でも、いざやってみるとそんな簡単にはいかなかったりする。アイデアコンペなんだけど、当時はコンセプチュアルなものが優先されたりしていたので、自分の考えもどんどんコンセプチュアルになって迷走しはじめたり。
あの時代のコンペは、良い意味でも悪い意味でも荒唐無稽に近いような、新しい建築みたいなものに対するモチべーションを掻き立ててくれるテーマがたくさんあって、そのテーマを解釈することが僕らのマインドセットにもなっていた。だから今回の「ガラスの家 ※4 」という課題は、新しい何かを掻き立てつつもこれからの時代性に深く思考を促すテーマだなと。そのワクワク感を学生さんや若い建築家に感じてもらいたいですね。
アイデアコンペが日本の建築家を
ユニークな存在にしている(五十嵐)
五十嵐:藤本さんは海外で審査員を務める機会もあると思いますが、向こうではアイデアコンペは多いのでしょうか。日本は世界的に見ても多いと思うのですが、実はそれが新しい発想を生み出すことに貢献している可能性があると感じていまして。
藤 本:たしかに。海外の大学は、コンセプチュアルな方向はそちらに全振りしている印象がありますね。謎の方法論になっていたりする。一方で、実務的なところを徹底的に教えるところもある。すぐ実施設計できますという風に。海外のアイデアコンペって、あまり聞かないですよね。その意味で、日本ではアイデアコンペがたくさんあって、それがコンセプトと建築をつなげる思考を鍛えているところはあるかもしれないですね。それが日本の建築家をユニークな存在にしている部分は確実にあると思う一方、世界を席巻しているサステナビリティやCO2などが日本ではすっぽり抜けている傾向にある。だからといって一気に現実性に振る必要はないけれど、抽象的にでも近づけていくことは重要だと思います。その間をうまくブリッジできるかどうかが、これからの時代、面白いと思いますね。
五十嵐:藤本さんと一緒に講評した「建築学生ワークショップ ※5 仁和寺」でも、リサイクルの可能性を求められて、1日だけ存在してゴミになるようなインスタレーションは急速にマイナスにとられるようになりましたからね。
藤 本:そうですよね。そこをどうやってクリエイティブに乗り越えていくかという意味では面白い流れだと思います。
五十嵐:そういえば、15年くらい前に「9坪ハウス ※6 」で一緒に審査員をしましたよね。1,000件近くの応募があって大変でしたが、あの時の藤本さんの選び方が印象的で、ちょっとバカっぽいというか、笑いのあるものをあえて選ぶというか…。
藤 本:数が多かったので、少し変わっていて面白いものや独特なものは残していき、なんとなくすぐに読み切れるものや形として成立していないものはどんどん落としていきました。上手にできていて優秀な作品は目に入るけど、さらにもう一声、なんかユニークな視点が欲しくなる。
五十嵐:単に優等生的なものから選んでも面白くない、というと言い方は変だけど、とにかく何かが違う。新しい歴史のページが開く感じがしないというか。
藤 本:そうですよね。「これだ!」という作品がない場合、なんとなくそういうものを残したくなりますが、結局、最終的には10件ぐらいには絞られる。だから「無理にたくさん選ばなくてもいいや」と思うと意外に開き直れて、候補からバンバンはずしていくようになりました。
五十嵐:学校ではA評価が取れても、コンペとなるとまた違いますよね。すごい数の中から残るわけですから。あと、出会いもあると思いますね。「その案と私が出会う」みたいな。
藤 本:たしかにそれはありますよね。でも一方で、同じようなアイデアでも建築として提案していく力の差が見えてくる。だからスポーツじゃないですけど、ベースの“建築力”のようなものを日々鍛えていくことで、二段階も三段階も違う力強い作品になったりする。ズバッと鮮やかなアイデアで行ける部分もあるけれど、やっぱり普段の積み重ねが如実に一枚のパネルに現れてくるという印象です。
五十嵐:審査する立場になるとわかりますからね。
藤 本:でも、応募していた頃は、何が選ばれるのか本当にわからなかった。評価基準も自分の人生の先もわからなくて、とにかく無我夢中でした。逆に「こういうのが評価されるだろう」という視点で傾向と対策を考えて作るとユニークな作品にならない。だから、その人ならではの日々の考えや発想力を信じてほしいなと思います。
五十嵐:話は変わりますが、若い頃に参加した実施コンペでは、どんな攻め方をされていましたか。
藤 本:当時はプロポーザルではなく、設計コンペだったじゃないですか。青森の美術館でもパネルをちゃんと作る感じで、設計課題に近かった。磯崎新さんが審査員をされた「せんだいメディアテーク ※7 」や「横浜港大さん橋国際客船ターミナル国際コンペ ※8 」もそうでしたよね。
五十嵐:そうですね。
藤 本:磯崎さんが勝った「なら100年会館 ※9 」のホールのパネルが全部「JA ※10 」にそのまま載っているのを見て、「これからの建築コンペは単に要望を満たすのではなく、さらにその先の時代を作るような建築が選ばれるんだ」っていう実感がすごくあった。多分、建築家みんながそれを感じて、ワクワクしていた時期だったと思うんです。コンセプチュアルに次の時代を形作るということをポジティブに考えながら、攻めていた気がします。
五十嵐:「メディアテーク」にしろ「横浜港」にしろ、90年代は時代を刷新するような案が選ばれていました。「京都駅ビル ※11 」もコンペでしたね。
藤 本:2000年代になって自分のモードが少し変わりました。「富弘美術館」や「邑楽町」などの群馬のコンペ ※12 は事務所を開設した頃で、複数のスタッフと一緒になって取り組みました。
五十嵐:新井さんがすごい仕掛けてこられて、画期的でしたよね。では、海外のコンペに臨むときはどんなことを考えていますか。
藤 本:海外は応募要項が膨大なのですが、英語を読みこむ訓練が僕もスタッフもできていなかったのに「とにかくやろう!」みたいな感じで。体制が整ってきたのは台湾タワー ※13 やベオグラードの「ベトン ハラ ウォーターフロント センター ※14 」を獲った2011年頃です。その少し後、モンペリエの「L’Arbre Blanc ※15 」のコンペがあって、どんどん挑戦するようになりました。ブダペストの「House of Music ※16 」もそう。海外のコンペというとお祭り的なところもあったけど、今では定期的に参加しています。
五十嵐:海外は参加資格などのハードルは低いのでしょうか。
藤 本:ヨーロッパではまず履歴書や実績などを送って、ショートリストに招待されないとダメなんです。「ベオグラード」や「ブダペスト」は完全オープンコンペでしたが、それって意外と珍しいことで。モンペリエの案件は最初、向こうから誘っていただき、後から僕らがチームに入った感じでした。誘ってくれたのがすごくいい建築家で、その後も一緒にやったりしています。フランスだとデベロッパーとチームを組むこともあって、単なる建築コンペじゃなくて、事業コンペ的なところがあるんですよね。そういう意味ではモンペリエを獲らせてもらったので、その後のいわゆる予選、プリクオリフィケーションっていうんですけど、それには通りやすくなりました。
五十嵐:そういえばブダペストはすごく藤本さん推しですよね(笑)。
藤 本:「House of Music」が大人気なんです。ハンガリーの人々の魂の中には音楽があると感じるのですが、その音楽の施設が非常にいい感じに完成したということで。実はハンガリーの2022年の「今年の人」にも選ばれたんですよ。いろんな偶然が重なったと思うのですが(笑)。
五十嵐:それはすごい(笑)。
藤 本:あと、同じ公園内に妹島和世さんと西沢立衛さんの「新国立ギャラリー ※17 」も計画されています。
五十嵐:ハンガリーの国家建築に藤本さんや妹島さん、西沢さんが絡んでいることが清々しいというか、建築の力をここまで信じてくれて「ありがとう」という感じですね。
藤 本:国際コンペと言えば、中国からも呼ばれることが増えてきていますね。
五十嵐:深圳の十大文化施設もコンペですか?
藤 本:そうです。コロナ禍だったのですが、深圳にたくさん文化施設を作ろうということで同時にいくつかありました。2つ3つ参加した中で博物館のコンペに勝てました。
五十嵐:いろいろお話を伺ってきましたが、今回の日本電気硝子さんのコンペでもテーマを決める際に話が出た人工知能系、例えば生成AIについてどのようにお考えですか。
藤 本:僕たちはどう使えるのか、スタディ中ですね。
五十嵐:これからかなり伸びると思いますが、みんなが模索していますよね。
藤 本:いろいろ試してみて、自分たちが考えていることの先が見えると面白いなあと思うんです。予想もできなかったものが出てくる、あるいは自分がやってきたことを再認識させられるとか。だから可能性として間口を開いておいていいと思っています。
五十嵐:想像もつかないものを見せてくれるかどうかがカギですよね。今のところ「◯◯風に作れ」という分には使いやすいだろうけれど、そこを突破してくれないと新しい価値を生み出せない。
藤 本:そうですよね。出てきたものを見て、「だったらこういうこともありえるんじゃないの」という感じで僕らがAIとコラボレーションしていくイメージを持っています。でも、もしアイデアコンペでそのまま使う人が出てくるなら、その人にとってもったいないなと思いますね。たとえば、コンピューターと会話をしながら発想がどんどん飛躍して、辿り着いた先にできたものを自分でプレゼンテーションする使い方は「あり」じゃないかな。うちはスタッフに「とにかく使ってみて」と言っているんですが、新しい何かを見つけられれば、まずはいいと思っています。最終的な価値判断は、やっぱり建築家がしていくわけですから。
*本記事は2023年9月時点のものです。

Profile
藤本 壮介(ふじもと そうすけ)
1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。
2014年フランス モンペリエ国際設計競技最優秀賞(L’Arbre Blanc) に続き、2015、2017、2018年にもヨーロッパ各国の国際設計競技にて最優秀賞を受賞。
国内では2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーに就任。2024年には「(仮称) 国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託」の基本設計者に特定。
主な作品に、ブダペストのHouse of Music (2021) 、マルホンまきあーとテラス 石巻市複合文化施設 (2021) 、白井屋ホテル (2020) 、L’Arbre Blanc (2019)、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013 (2013)、House NA (2011)、 武蔵野美術大学美術館 図書館 (2010)、House N (2008) など。
Profile
五十嵐 太郎(いがらし たろう)
1967年フランス・パリ生まれ。1990年東京大学工学部 建築学科卒業。1992年同大学院修士課程修了、博士(工学)。 現在、 東北大学大学院教授。
あいちトリエンナーレ2013芸術監督、 第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナーを務める。
「インポッシブル・アーキテクチャー」 「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」等の展覧会を監修。
第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞、 2018年日本建築学会教育賞(教育貢献) を受賞。『日本建築入門』(筑摩書房)、『被災地を歩きながら考えたこと』 (みすず書房)、『モダニズム崩壊後の建築』 (青土社)、『現代建宣言文集』(共編著、 彰国社) ほか著書多数。
- ※1:青森の三内丸山遺跡に隣接する美術館。2006年開館。オープンコンペは2000年に行われ、建築家・青木淳氏の案が最優秀に。藤本案は第2位(優秀賞)となり注目を集めた。
- ※2:受賞作品については、P23「過去受賞者からのメッセージ」を参照。
- ※3:大分の個人邸。2008年竣工。藤本氏初期の作品。3つの箱が入れ子になった形状で、内側2つがインテリア、外側が庭となり、庭は半外部のような曖昧な空間。
- ※4:第30回空間デザイン・コンペティションの課題「未来社会を切り拓く、21世紀のガラスの家」を指す。
- ※5:NPO法人アートアンドアーキテクトフェスタ主催の地域滞在型ワークショップ。毎年、建築を学ぶ学生が全国から集まり、1日だけの小さな建築空間を作り上げる。
- ※6:建築家・増沢洵氏による狭小住宅を原型とする最小限住宅。Boo-Hoo-Woo.comと文藝春秋社TITLE(休刊)が中心となり2005年から3年間コンペを開催。2006年に藤本氏と五十嵐氏が審査員を務めた。
- ※7:仙台にある図書館やギャラリーなどを併設した公共施設。2001年開館。1995年に設計競技が行われ、建築家・伊東豊雄氏が最優秀賞を受賞した。
- ※8:日本開催の国際コンペとしては過去最大規模。1995年に実施。最優秀に選ばれたのは、英国在住の建築家ユニットFOA(Foreign Office Architects)案。
- ※9:奈良市制100周年を記念して建設された多目的ホール。1999年竣工。1992年の国際コンペにて建築家・磯崎新氏の案に決定した。
- ※10:The Japan Architectの略称。1956年に日本の建築を海外に向けて紹介する唯一の英文媒体として創刊。
- ※11:1997年開業。建築家・安藤忠雄氏をはじめ国内外から建築家7名が指名され、1990年に設計競技を開催。建築家・原広司氏の案に決定した。
- ※12:群馬県庁職員だった新井久敏氏が中心となり企画した設計競技を指す。「新富弘美術館」は建築家・ヨコミゾマコト氏の案が、「邑楽町役場庁舎」は建築家・山本理顕氏の案が選ばれた。
- ※13:台湾・台中市で予定されていた高層建築の一般呼称。2011年に行われた国際コンペで、藤本氏が最優秀に選ばれた。
- ※14:セルビア・ベオグラードの設計競技。2011年に行われ、藤本案が一位に輝いた。
- ※15:フランス・モンペリエのレジデンシャルタワー。2019年竣工。2014年の国際競技で藤本氏とフランスの若手建築家達のチームの案が最優秀を獲得。一本の木のように、幹となるタワーから枝として伸びるバルコニーやファサードが特徴的。
- ※16:ハンガリー・ブタペスト中心部にあるリゲットパークに、2022年にオープンした音楽複合施設。2014年の国際設計競技で藤本氏が一位を獲得した。
- ※17:House of Musicと同じ「リゲット・ブタペスト・プロジェクト」の一環として建設予定のギャラリー。妹島和世氏+西沢立衛氏による建築家ユニットSANAAが設計。
記念展

今年30回目を迎えた「空間デザイン・コンペティション」。 これまで支えてくださった皆さまに感謝の気持ちを込めて開催する記念展 「空間デザイン・コンペティションと10組の建築家展」では、 コーディネーターの五十嵐太郎氏の協力のもと、「提案部門」過去受賞者から選ばれた建築家10組をご紹介しました。
出展者(敬称略)
- 島田 陽 /
- 平田 晃久 /
- 藤本 壮介 /
- 勝矢 武之 /
- 古澤 大輔 /
- 久保 秀朗・都島 有美 /
- 百枝 優 /
- 工藤 浩平 /
- 冨永 美保 /
- 藤井 玄徳・富樫 由美 /
- 協力:五十嵐太郎
- 島田 陽 - Yo Shimada
-
1972年兵庫県生まれ。1997年京都市立芸術大学大学院修了後、直ち にタトアーキテクツ設立。2021年より京都市立芸術大学准教授。
■主な作品:六甲の住居(2012)、石切の住居(2013)、ハミルトンの住居(2016)、宮本町の住居(2017)他。
■主な受賞: Asia Pacific Property Award Architecture Single Residence Highly Commended、LIXILデザインコンテス ト2012金賞、第29回吉岡賞(いずれも2013)。日本建築設計学会賞 大賞、National Commendation, AIA National Architecture Awards(共に2016)。Dezeen Awards 2018 House of the Year(2018)等。
■著書:『島田陽住宅/YO SHIMADA HOUSES』『日常の設計の日常』 『7iP #04 YO SHIMADA』等。
- 平田 晃久 - Akihisa Hirata
-
1971年大阪府生まれ。1997年京都大学大学院工学研究科修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務の後、2005年平田晃久建築設計事務所を設立。現在、京都大学教授。
■主な作品:桝屋本店(2006)、sarugaku(2008)、Bloomberg Pavilion(2011)、Tree-ness House(2017)、太田市美術館・図書館(2017)、八代市民俗伝統芸能伝承館(2021)等。
■ 主な受賞:第19回JIA新人賞(2008)、第13回ベネチアビエンナーレ 国際建築展金獅子賞(2012、共働受賞)、村野藤吾賞(2018)、BCS 賞(2018)、日本建築学会賞(2022)等多数受賞。
■著書:Discovering New(TOTO出版)、JA108 Akihisa HIRATA 平田晃久2017→2003(新建築社)等。
- 藤本 壮介 - Sou Fujimoto
-
1971年北海道生まれ。東京大学工学部建築学科卒業後、2000年藤本壮介建築設計事務所を設立。
■主な作品:House of Music、マルホンまきあーとテラス(共に2021)、 白井屋ホテル(2020)、L’Arbre Blanc(2019)、サーペンタイン・ ギャラリー・パビリオン2013(2013)、House NA(2011)、武蔵野美術大学美術館・図書館(2010)、House N(2008) 等。
■主な受賞:2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞に続き、2015、2017、2018年にも欧州各国の国際設計競技で最優秀賞を受賞。 2025年日本国際博覧会の会場デザインプロデューサーに就任。2021 年に飛騨市のCo-Innovation University(仮称)キャンパスの設計者に選定される。
- 勝矢 武之 - Takeyuki Katsuya
-
1976年兵庫県生まれ。1998年京都大学工学部建築学科卒業。2000 年同大学院修士課程修了後、日建設計入社。2008年日経スペースデザ イン。2010年日建設計復帰。現在、同社設計監理部門ダイレクター。
■主な作品:FCバルセロナ カンプノウ・バルセロナ(2028予定)、渋谷ス クランブルスクエア/渋谷スカイ(2019)、有明体操競技場(2019)、上 智大学ソフィアタワー(2017)、マギーズ東京(2016)、港区白金の丘学 園(2014)東亜道路工業本社ビル(2015)、木材会館(2009)など。
■主な受賞:日本空間デザイン賞 KUKAN OF THE YEAR(2020)、 ウッドデザイン賞 最優秀賞(2020)、the DFA(Design for Asia) Gold Award and DFA Grand Award(2010)他
- 古澤 大輔 - Daisuke Furusawa
-
1976年東京都生まれ。2000年東京都立大学工学部建築学科卒業。 2002年東京都立大学大学院修士課程修了。同年、メジロスタジオ設立 (2013年、リライト_Dに組織改編)。2013年~日本大学理工学部建築学科。現在、日本大学理工学部建築学科准教授。
■主な作品:下高井戸の産婦人科(2020)、古澤邸(2019)、中央線高架下プロジェクト(2014)、アーツ千代田3331(2011)等。
■主な受賞:JIA日本建築大賞(2020)、日本建築設計学会賞(2020)、 JCDデザインアワード金賞(2015)、日本建築学会作品選奨(2012)、 SDレビュー朝倉賞(2011)等。
- 久保 秀朗 - Hideaki Kubo
-
1982年千葉県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業、Sint Lucas Architectuur(Belgium)、東京大学大学院新領域創成科学研究科 修了。2011年久保都島建築設計事務所を共同設立。
- 都島 有美 - Yumi Tsushima
-
1982年愛知県生まれ。九州大学工学部建築学科卒業、Sint Lucas Architectuur(Belgium)、九州大学大学院人間環境学府修了。 2011年久保都島建築設計事務所を共同設立。
■主な受賞
日本建築学会作品選集新人賞(2017)、AR AWARDS 2016入賞(2016)、JCD DesignAward金賞(2016)、iF DESIGN GOLD AWARD(2022)
- 百枝 優 - YU Momoeda
-
1983年長崎県生まれ。2006年九州大学芸術工学部環境設計学科卒 業。2009年横浜国立大学大学院/建築都市スクールY-GSA修了。 2010年隈研吾建築都市設計事務所入社。2014年百枝優建築設計事務所設立。2023年九州大学BeCAT担当教員。
■主な作品:Agri Chapel(2016)、Hafh SAI(2018)Four Funeral Houses(2018)、Bottomless Window(2018)、 Farewell Platform(2021)等
■主な受賞:SD Review 新人賞(2006)、日本建築学会作品選集新人賞(2018)、ABB LEAF Awards入選(2017) 準大賞(2018)、AREmerging Architecture Awards 入選(2016) 準大賞(2018)、DFA Design For Asia Awards 大賞+金賞(2017) 大賞 (2021)、日本建築美術工芸協会芦原義信賞(2021)
- 工藤 浩平 - Kohei Kudo
-
1984年秋田県生まれ。2005年国立秋田高専卒業。2008年東京電 機大学卒業。2011年東京藝術大学大学院美術研究科修了。2012年~ 2017年SANAA勤務。2017年工藤浩平建築設計事務所を秋田と東 京に二拠点で設立。東京電機大学、東京理科大学、多摩美術大学非常 勤講師。
■主な作品:東松山の家(2018)、プラス薬局みさと店(2019)、楢山の 別邸(2020)、佐竹邸(2021)、大阪・関西万博休憩所(2025)他。
■主な受賞:JIA東北住宅大賞2021住宅賞、2022年日本建築学会作品選集新人賞、住宅建築賞2023入賞
- 冨永 美保 - Miho Tominaga
-
1988年東京都生まれ。横浜国立大学大学院Y-GSA修了。東京藝術大 学美術学科建築科教育研究助手を経て、2014年にトミトアーキテク チャを設立。
■主な作品:CASACO(2016)、真鶴出版2号店(2018)、泉大津市立図 書館SHEEPLA(2021)※フジワラテッペイアーキテクツラボと協働 主な受賞:第1回JIA神奈川デザインアワード優秀賞受賞、SDレビュー2017入選、第2回Local Republic Award最優秀賞受賞、2018年 ヴェネチアビエンナーレ出展。
■大切にしているのは、日常を観察して、さまざまな関係性の編み目のな かで建築を考えること。小さな住宅から公共建築、パブリックスペース まで、土地の物語に編みこまれるような、多様な居場所づくりを行って います。
- 藤井 玄徳 - Harunori Fujii
-
1988年東京都生まれ。2015年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。2016年藤本壮介建築設計事務所。2018年横井創馬建築 設計事務所。2021年マーマル建築設計事務所設立。
■主な受賞:第8回ダイワハウスコンペティション 優秀賞、第20回・第28回 空間デザインコンペティション 入選、新建築住宅設計競技2022 二等
- 富樫 由美 - Yumi Togashi
-
1990年新潟県生まれ。2016年日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。2016年海法圭建築設計事務所。現在、マーマル建築設計事務所。
- 五十嵐太郎 - Taro Igarashi
-
1967年フランス・パリ生まれ。建築史・建築批評家。現在、東北大学大学院教授。
1992年東京大学大学院修士課程修了。あいちトリエンナーレ2013芸術監督、第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展日本館コミッショナーを務める。「インポッシブル・アーキテクチャー」「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」「装飾をひもとく~日本橋の建築・再発見~」などの展覧会を監修。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞、2018年日本建築学会教育賞(教育貢献)を受賞。『誰のための排除アート?』(岩波書店)、『新宗教と巨大建築』(青土社)、『増補版 戦争と建築』(晶文社)ほか著書多数。
詳細
開催日時:2023年12月6日(水)~12月11日(月) 10:00~17:00(最終日は16:00まで)
会場:建築会館ギャラリー
〒108-0014 東京都港区芝5丁目26-20
最寄り駅:JR「田町駅」、都営地下鉄「三田駅」