
2025.05.15
建築家インタビュー
記念対談:藤本壮介 ✖ 五十嵐太郎(後編)
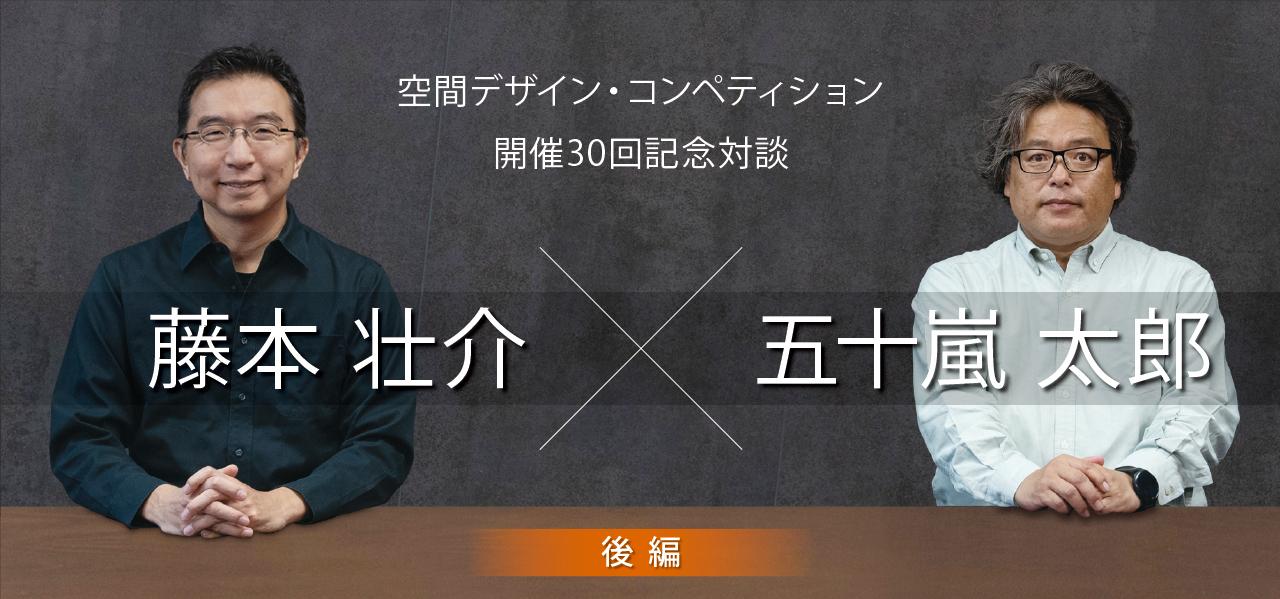
「空間デザイン・コンペティション」開催30回を記念し、第23回からコーディネーターを務める建築批評家・五十嵐太郎氏と、かつての本コンペ受賞者で第30回審査委員長、そしていまや世界的に活躍する建築家・藤本壮介氏との対談が実現。当時の受賞作品や思考していたこと、建築コンペ全般にまつわる話から生成AIの可能性に至るまで、興味深いお話を和やかに語っていただきました。(前編はこちら)
※ 2023年9月の対談を記事にしたものです。
※「空間デザイン・コンペティション」は日本電気硝子主催、電気硝子建材が共催した建築設計競技。ガラスと空間にちなんだ課題を基にアイデアを競う「提案部門」と、日本電気硝子製の建材製品を使用した施工例から選出する「作品例部門」の2部門にて、1994年から2023年まで開催しました(第21回および第23回以降は提案部門のみ)。
次の時代を形作ることを
ポジティブに考えながら
攻めていた (藤本)
五十嵐 話は変わりますが、若い頃に参加した実施コンペでは どんな攻め方をされていましたか。
藤 本 当時はプロポーザルではなく、設計コンペだったじゃないですか。青森の美術館でもパネルをちゃんと作る感じで、設計課題に近かった。磯崎新さんが審査員をされた「せんだいメディアテーク *7」や「横浜港大さん橋国際客船ターミナル国際コンペ *8」もそうでしたよね。
五十嵐 そうですね。
藤 本 磯崎さんが勝った「なら100年会館 *9」のホールのパネルが全部JA *10にそのまま載っているのを見て、「これからの建築コンペは単に要望を満たすのではなく、さらにその先の時代を作るような建築が選ばれるんだ」っていう実感がすごくあった。多分、建築家みんながそれを感じてワクワクしていた時期だったと思うんです。コンセプチュアルに次の時代を形作るということをポジティブに考えながら攻めていた気がします。
五十嵐 「メディアテーク」にしろ「横浜港」にしろ、90年代は情報化を意識して、時代を刷新するような案が選ばれていました。「京都駅ビル *11」もコンペでしたね。
藤 本 2000年代になって自分のモードが少し変わりました。「富弘美術館」や「邑楽町」などの群馬のコンペ *12は事務所を開設した頃で、複数のスタッフと一緒になって取り組みました。
五十嵐 新井さんがすごい仕掛けてこられて画期的でしたよね。では、海外のコンペに臨むときはどんなことを考えていますか。
藤 本 海外は応募要項が膨大なのですが、英語を読みこむ訓練が僕もスタッフもできていなかったのに「とにかくやろう!」みたいな感じで。体制が整ってきたのは「台湾タワー *13」やベオグラードの「ベトン ハラ ウォーターフロントセンター *14」を獲った2011年頃です。その少し後、モンペリエの「L'Arbre Blanc *15」のコンペがあって、どんどん挑戦するようになりました。ブダペストの「House of Music *16」もそう。海外のコンペというとお祭り的なところもあったけど、今では定期的に参加しています。
五十嵐 海外は参加資格などのハードルは低いのでしょうか。
藤 本 ヨーロッパではまず履歴書や実績などを送って、ショートリストに招待されないとダメなんです。「ベオグラード」や「ブダペスト」は完全オープンコンペでしたが、それって意外と珍しいことで。モンペリエの案件は最初、向こうから誘っていただき、後から僕らがチームに入った感じでした。誘ってくれたのがすごくいい建築家で、その後も一緒にやったりしています。フランスだとデベロッパーとチームを組むこともあって、単なる建築コンペじゃなくて、事業コンペ的なところがあるんですよね。そういう意味ではモンペリエを獲らせてもらったので、その後のいわゆる予選、プリクオリフィケーションっていうんですけど、それには通りやすくなりました。
五十嵐 そういえばブダペストの都市はすごく藤本さん推しですよね(笑)。
藤 本 「House of Music」が大人気なんです。ハンガリーの人々の魂の中には音楽があると感じるのですが、その音楽の施設が非常にいい感じに完成したということで。実はハンガリーの2022年の「今年の人」にも選ばれたんですよ。いろんな偶然が重なったと思うのですが(笑)。
五十嵐 それはすごい(笑)。
藤 本 あと、同じ公園内に妹島和世さんと西沢立衛さんの 「新国立ギャラリー *17」も計画されています。
五十嵐 ハンガリーの国家建築に藤本さんや妹島さん、西沢さんが絡んでいることが清々しいというか、建築の力をここまで信じてくれて「ありがとう」という感じですね。
藤 本 国際コンペと言えば、中国からも呼ばれることが増えてきていますね。
五十嵐 深センの十大文化施設もコンペですか?
藤 本 そうです。コロナ禍だったのですが、深センにたくさん文化施設を作ろうということで同時にいくつかありました。2つ3つ参加した中で博物館のコンペに勝てました。
想像もつかないものを
見せてくれるかどうか
ーそれがAIのカギ (五十嵐)
五十嵐 いろいろお話を伺ってきましたが、今回の日本電気硝子さんの空間コンペでもテーマを決める際に話が出た人工知能系、例えば生成AIについてどのようにお考えですか。
藤 本 僕たちはどう使えるのかスタディ中ですね。
五十嵐 これからかなり伸びると思いますが、みんなが模索していますよね。
藤 本 いろいろ試してみて、自分たちが考えていることの先が見えると面白いと思うんです。予想もできなかったものが出てくる、あるいは自分がやってきたことを再認識させられるとか。だから可能性として間口を開いておいていいと思っています。
五十嵐 想像もつかないものを見せてくれるかどうかがカギですよね。今のところ「◯◯風に作れ」という分には使いやすいだろうけれど、そこを突破してくれないと新しい価値を生み出せない。
藤 本 そうですよね。出てきたものを見て「だったらこういうこともありえるんじゃないの」という感じで僕らがAIとコラボレーションしていくイメージを持っています。でも、もしアイデアコンペでそのまま使う人が出てくるなら、その人にとってもったいないなと思いますね。たとえば、コンピューターと会話をしながら発想がどんどん飛躍して、辿り着いた先にできたものを自分でプレゼンテーションする使い方は「あり」じゃないかな。うちはスタッフに「とにかく使ってみて」と言っているんですが、新しい何かを見つけられれば、まずはいいと思っています。最終的な価値判断は、やっぱり建築家がしていくわけですから。
*7 せんだいメディアテーク
仙台にある図書館やギャラリーなどを併設した公共施設。2001年開館。1995年に設計競技が行われ、建築家・伊東豊雄氏が最優秀賞を受賞した。
*8 横浜港大さん橋 国際客船ターミナル国際コンペ
日本開催の国際コンペとしては過去最大規模。1995年に実施。最優秀に選ばれたのは英国在住の建築家ユニットFOA(Foreign Office Architects)案。
*9 なら100年会館
奈良市制100周年を記念して建設された多目的ホール。1999年竣工。1992年の国際コンペにて建築家・磯崎新氏の案に決定した。
*10 JA
The Japan Architectの略称。1956年に日本の建築を海外に向けて紹介する唯一の英文媒体として創刊。
*11 京都駅ビル
1997年開業。建築家・安藤忠雄氏をはじめ国内外から建築家7名が指名され、1990年に設計競技を開催。建築家・原広司氏の案に決定した。
*12 群馬のコンペ
群馬県庁職員だった新井久敏氏が中心となり企画した設計競技を指す。「新富弘美術館」は建築家・ヨコミゾマコト氏の案が、「邑楽町役場庁舎」は建築家・山本理顕氏の案が選ばれた。
*13 台湾タワー
台湾・台中市で予定されていた高層建築の一般呼称。2011年に行われた国際コンペで、藤本氏が最優秀に選ばれた。
*14 ベトン ハラ ウォーターフロント センター
セルビア・ベオグラードの設計競技。2011年に行われ、藤本案が一位に輝いた。
*15 L'Arbre Blanc
フランス・モンペリエのレジデンシャルタワー。2019年竣工。2014年の国際競技で藤本氏とフランスの若手建築家達のチームの案が最優秀を獲得。一本の木のように、幹となるタワーから枝として伸びるバルコニーやファサードが特徴的。
*16 House of Music
ハンガリー・ブタペスト中心部にあるリゲットパークに、2022年にオープンした音楽複合施設。2014年の国際設計競技で藤本氏が一位を獲得した。
*17 新国立ギャラリー
House of Musicと同じ「リゲット・ブタペスト・プロジェクト」の一環として建設予定のギャラリー。妹島和世氏+西沢立衛氏による建築家ユニットSANAAが設計。
◇ Profile

※本記事は「環85号(2024年発行)」の記事を再掲したものです。
※本誌はこちらからご覧いただけます。
Share
